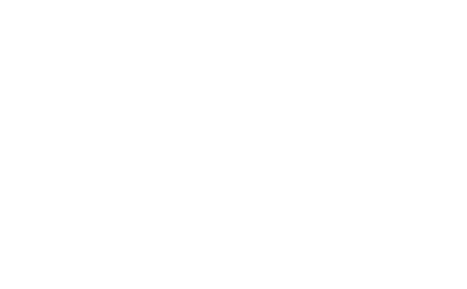第1章 プロローグ
「やったー!!できましたよ。見てください、黒い縞々が消えています。できましたよ。できましたよ。完成です。」
私は、興奮のあまり大きな声で叫んだ。
その大きな声は、人影のない、冷え切った薄暗い実験室の中でこだました。そしてそれは、LEDを半永久的に光らせることができるかもしれない夢の技術、『電解コンデンサーレス・テクノロジー』が生まれた瞬間であり、私がこれから歩む、人生をかけた戦いの幕開けでもあった。
もちろん、その時はそんなことは、これっぽっちも考える事なく、ただただ、この世紀の発明に心を躍らせていた。
2011年2月、私は、中国広東省の薄暗い実験室の中にいた。
外は、亜熱帯地域に属する広東省では珍しく、しんしんと雪が降っていた。1年の内11ヶ月の気温は30度を超える、中国南部のこの地域では、建物には防寒対策は何一つなく、建物全体が雪の冷たさと同化していた。
あたかも大型冷蔵庫の中にいるような冷気の中で、私達は、手入れもろくにされていない、骨董品のような古ぼけた計測器が数個並んでいる4畳半ほどの小さな実験室の中にいた。
私の目の前には、過去、たった一人の開発で世界の8割を握るなどの数々の伝説を作った、天才技術者の北島がいた。彼は、その古ぼけている上に、中国語表示されていて、本当に理解できているのかすら不思議な設備の前で、何度も何度も繰り返し実験を重ねていた。
「おかしいなー、これで完成のはずなのだけど…」
彼のつぶやきを、私は今日何度聞いたことだろう。
商品の設計などしたこともない私は、彼のつぶやきに対して、ただただ、励ますしか能がない存在であった。
寒さは、容赦なく襲いかかってくる。午前中、実験室の選定を一度間違えて、雪の中を彷徨ったため、服は雪に濡れ、靴下から襲いかかってくる冷たさは、40歳を超えて中年の真っ只中にいる私達にはあまりに過酷であった。
作業開始から、すでに6−7時間は経過しただろうか。状況の進展は見られない。突き刺さる寒さと芯まで冷え切った体は、私に即座のギブアップ宣言を要求していた。
「もうやめましょう。ありがとうございました。食事でも行きましょう」
どれだけこの言葉を口走ろうと思ったことか。
これは仕事ではない。完成しなくても、誰にも迷惑はかからないし、義務もなければ納期もない。
しかも目の前で苦労しているのは、すでに会社を去って10年経つ年上の大先輩のエンジニアであり、旅行の日程を1日割いて、私を手伝ってくれているだけに過ぎないのだ。
私が一言、この言葉を発すれば、私と彼は、すぐさまこの寒さからも解放され、暖かい夕食と美味しいお酒が待つ馴染みの日本料理店に向かうことが出来るのだ。そして、明日から、何事もなく普通の生活が始まるだけ。失うものは何一つない。
しかし、私は最後までこの言葉を口に出すことをためらっていた。もしかしたら、それが出来るかもしれないという淡い期待が、私にその言葉を吐くことを許してくれなかった。そして、今、その言葉を吐いたら、私達人類は、その希望を二度と手にすることはできないだろうと思っていた。
私が完成を待っていたのは、LED電球を半永久に光らせることが出来るかもしれない夢の技術であった。
全てのLED電球には、必ず寿命が最初から決められている『電解コンデンサー』という電子部品が使用されている。その部品は、『寿命』が決められているだけではなく、その寿命は、LED電球自らが発する熱によって、急激に短くなるのである。
誰もがわかりきった事実ではあるものの、それを使用しないでLED電球を作ることを皆諦めていた。それは、LED電球における基本中の基本『いろはのい』だからである。
そしてそのことによって、本来半永久に光るはずのLEDが、その実力を全く発揮できないまま、壊れて、捨てられているのである。
過去、私は知っている限りのありとあらゆる技術者に、この電子部品を使わないようにできないのかと聞いて回った。
しかし、その全ての答えは、「NO」であり、ほぼ全員が全く同じ不可能な理由を懇切丁寧に説明してくれた。それほど、エンジニアの世界の中では共通の知識であり、まさに『いろはのい』であった。
その中で、唯一、「YES」と答えたのが、目の前にいる、すでに退職して現役を引退してしばらく経っていた北島なのだ。
私は、今までも彼が、たった一人で不可能を可能にしてきた奇跡のような開発をこの目で見てきた。
その彼は、私の話を聞くや、間髪を入れず「出来ると思う」と答えた。
その今までの経験が、私に「もう、やめましょう」の一言を言わせることをためらわせていた。
しかし、改善しない状況と、今まで誰もが「出来るはずがない」と言い切った難易度の高さに、私の心は、半ば折れかけていた。
この検証実験において、最終的な成功の鍵を握る最難関ポイントは、人間の目にはわからない高速な光の点滅(フリッカー)の消滅であり、この、間借りの古ぼけた設備では、専門で高価なフリッカー計測器などあるはずもなく、私達は、個人所有のiPhoneを使ってそれを測っていた。
フリッカーがあると、そのiPhoneの画面に黒い縞々模様が発生するのである。しかし、その黒い縞々が何度やっても、ある段階から消えないのである。
時計の針は、すでに夜9時を回っている。
私は、ついにこの最後の言葉を言う決心がついた。こんなに時間まで、この寒さの中で、しかも大先輩に対して実験を継続させることはできない、そう思った。(ちなみに北島は、自分からは、一度たりとも「やめよう」とは言わなかったが。)
そして、今まで自分の中に膨れ上がった期待に決別する悲しさに、私は、大きなため息とともに天を仰いだ。本当に天を仰いだのである。その時である。
「あっ!!」
私の目にあるものが飛び込んで来た。それは、実験室の上にある、『蛍光灯』。
私は、慌てて、カバンに入っている、今朝届いた1日遅れの日経新聞海外版(海外は1日遅れで配達される)をくるくると筒状に丸め、その中にiPhoneのカメラ部分を収め、恐る恐る画面を覗き込んだ。
そして、大きな声で叫んだ。
「やったー!!できましたよ。見てください、黒い縞々が消えています。できましたよ。できましたよ。完成です」
なんと、蛍光灯が放つ、ちらつきがiPhoneのカメラに入って、黒い線が発生していたのである。
しっかりと研究設備の整った日本の実験室ではありえない、そして、そういう設備での実験に慣れていた私達日本人が陥っていた、なんとも基本的な盲点だった。
かくして、これが人類が経験したことがないほど、長く光り続ける電球、そして、世界中から電球のゴミを一掃できるかもしれない夢の技術、『電解コンデンサーレス・テクノロジー』が、世の中に産声をあげた瞬間だった。