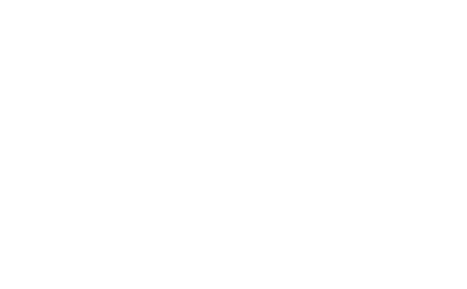第9章 出陣準備2(火の色)
「LEDの光が嫌いだ」という人は多い。
「眩しい」、「冷たい感じ」、「ギラついている」、「白っぽい」、「色が硬い」、「疲れやすいような気がする」、といった声をよく聞く。
これは、LEDの発光原理の違いから来ている。LEDは、だいたい0.3mmほどの大きさのものが発光している。0.3mmのシャーペンの先が、ものすごい光を放っているようなものである。眩しくないはずがない。
白熱電球は、フィラメントが3000度程の高熱で温められている。小さなキャンプファイヤーのようなものと言っても良いかもしれない。実際、触れないくらい熱いし、暖かい感じはする。しかし、LEDは、レーザーのようなものでかなり人工的である。硬い、冷たい、リラックスできない、というのは人類が今まで見て来た光とは、かなり違うからなのだと思う。人間の感覚や、言葉の表現力というのは、本当にすごいものとつくづく思う。
『光』の質へのこだわりとして、私たちは非常にチャレンジングな挑戦をしてみた。LEDである以上、発光原理は変わらないが、それを少しでも和らげることによって、LEDの光を好きになってもらいたいと考えたのである。
私たちは、21世紀の光、LEDに『暖かみ』を持たせることができないかを考えた。暖かみのある光というのは、ズバリ『炎の色』である。LEDで火の色を再現するべく取り組んだのである。
火の色が嫌いだという人はあまりいない。大体の人間は、ともしびのような火を見ると“ホッと”する。火の色などのオレンジ色の光を見ると、人間は副交感神経が優位になり、リラックス効果があるという。
これは、考えてみれば当然かもしれない。人間は、はるか太古の昔、原始時代から火によって守られてきたからだ。鋭い爪も牙もなければ、チーターのように早く走ることもできない人類は、火の力によって外敵やウイルスなどから守られてきた。専門的なことはわからないが、火の色を見て安心するのは、遺伝子的に組み込まれていると思っても不思議ではない。
しかしながら、LEDで火の色を実現するという開発は、簡単な事ではなかった。なぜなら、LED電球は青色LEDを使用している。先ほどの演色性の開発でも触れたが、青色から反対のオレンジ色を作り出すのは難しいのである。また、単にオレンジ色を作れば良いというものではない。自然の炎の色の色味を合わせるのに、何度も繰り返し試作を行なった。開発パートナーは、彩と同じ中国の設計会社であった。納得いくまで、何度も訪問し確認した。彼は、無茶とも言える私の要求に対し、根気よく最後まで付き合ってくれ、そして見事に私の要求に答えてくれた。
しかし、開発はここで終わりではなかった。LEDの光は、直進性が強いために光が前にしか光らずどうしてもレーザーのような機械的な光となってしまう。炎のように全体に広がるような優しい光にならないのである。そこで、光を全方向に光らせるような対策を講じる必要があった。
今までの私たちの電球は、すべて白いガラスの内側をすりガラスのようにして、光を拡散させることで、乱反射を起こし光の拡散をさせていた。しかし、今回の火の色は、白いカバーを覆ってしまうとせっかく完成した火の色の温かい色味が消えてしまうのである。火の色の電球を作るには、クリアガラスである必要があった。しかし、それは非常に困難な挑戦でもあった。
点発光の光を拡散させる方法として、透明なガラスや樹脂をレンズのように屈折させて光を広げるやり方を選択した。この方法は、他のLEDメーカーも採用しているが、実は大きな課題があった。この方法は、光を拡散させることはできるのだが、どうしても、解決できない問題があった。
それは、レンズを通すことによって“影”ができてしまうのである。光を壁や地面に映した時に、どうしても光の濃淡ができてしまうのである。
様々な試行錯誤を行い、レンズの形を検証した。そして花びらのようなプリズムカット構造をとることとした。これが最も影の濃淡ができにくくコントロールしやすい構造であったためである。しかしながら何度やっても影が消えない。そこで花びらの枚数と角度を微妙に調整することによって、影のない美しいグラデーションの光をついに実現することができたのである。
面白い事に、影の濃淡ができないことのみを追求した結果に出来上がった、電球の内部に組み込まれたプリズムカットレンズは、まるでダイヤモンドカットのような美しさを持った。この結果、(まさしく結果的に)火の色電球は、「照明器具に入れずに、外に出しても鑑賞できる美しさ」と称されるようになった。
人が生み出すもの、自然界のもので、機能を極限までに追求すると、そこに『機能美』なるものが出てくるというが、火の色電球は、その機能美のほんの一部を体現した、全く新しい商品として誕生する事になったのである。